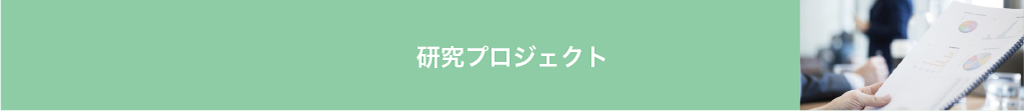2024年度

毎年4月に公募により募集。それぞれのテーマに基づいた議論の場を提供するにとどまらず、必要とされるITに関する情報を提供していきます。
-
ビジネスデータ研究会
昨今AIの活用にも注目が集まっており、2024年度はAIを用いたビジネスへのデータ利活用にもアプローチしたいと考えています。
AI活用には信頼あるデータが必要であり、回答には納得あるプロセスを経る必要があります。また、生成されたデータもまた信頼を求めるものです。
本研究会では、(A)ビジネスドリブンでデータの在り方、(B)データドリブン(活用)に至るまでの課題、(C)AI活用を含めた納得性のある結果を得るためのプロセス、 あるいは(D)AIにも使えるほどの信頼性のあるデータとはどんなものなのか、以上4つを研究テーマとして取り組みます。
報告動画はこちら»
-
ITインフラ研究会
ビジネスに貢献するITインフラの研究
ビジネス・最新IT動向の変化をふまえたインフラ計画策定、ビジネスの柔軟性・俊敏性のベースとなるITインフラ技術/構築/運用、それらを実現する組織・人材育成について研究します。
研究テーマ:
・ITインフラ領域全般の企画・統制・組織・人材育成等の検討
・ITインフラ技術のトレンドならびにビジネス現場での活用事例の収集
・ ITインフラ構築・運用の現場で活かせるようなノウハウや知見の共有等
報告動画はこちら»
-
サービスマネジメント
研究会
サービスマネジメントの進化・変革に関する研究
運用保守とは、単なるオペレーションや、言われたとおりにシステムを作ること、だけではないはずです。顧客の期待に応えられるサービスを提供することが運用保守であり、サービスマネジメントそのものです。
「新しいサービスの提供」や「顧客指向での問題解決」に向けて、皆さんの”経験・知識・想い”を持ち寄り、「これまでにない価値の発見・創出」にむけて”知見”を得る活動を行います。
報告動画はこちら»
-
企業リスクマネジメント
研究会
企業におけるリスクマネジメントについての研究
企業におけるリスクマネジメントについて有識者や参加企業の取り組みを基に、自社への適用や提言、企業の枠を超えた取り組みについて研究・情報交換をすることを目的とします。成果物の作成は目的としません。また、各分科会では様々なテーマを取り上げ、研究・議論・情報交換をします。
研究テーマ案:情報セキュリティマネジメント、サイバーセキュリティ等
報告動画はこちら»
-
IT投資ポートフォリオ
研究会
デジタル時代に対応したIT予算・IT投資管理の検討
業務プロセスの効率化等、様々な領域で積極的なIT投資が行われている一方、投資案件を担うIT人材不足により人月単価は上昇、加えて海外SaaSを中心とした値上げも無視できない状況です。こうした中、経営や事業戦略と整合したIT戦略の立案、IT投資案件の優先順位付け、IT予算の策定、予実管理精度の向上、IT費用の可視化、投資対効果の説明・評価等、社内外の様々なステークホルダー要求に応えていかなければなりません。
今年度も予算策定プロセスの効率化、高度化、維持・運用費の低減について継続して深堀りします。
報告動画はこちら»
-
組織力強化研究会
DXを推進するための組織力強化に向けた研究
今やデジタル化やイノベーションはあらゆるビジネスに不可欠であり、スピーディーなサービス提供や展開が゙要求されています。これらを自社のIT部門やIT担当者だけで担うにはもはや限界にきており、デジタル時代におけるIT・DX組織のあり方が問われるようになっています。本研究会では、デジタル化時代に則したIT組織体制やマネジメントとは何か、この流れをベースに下記領域ごとの分科会にてテーマを選定いただき、先進企業の事例ヒアリングやメンバーとディスカッションを通して研究します。
報告動画はこちら»
-
システム開発・保守QCDs研究会
システム開発における品質・コスト・工期・生産性についての改善
システム開発・保守における品質・コスト・工期・生産性の向上及び改善にむけた取組みについて、各社、事例発表を行います。事例発表後、テーマごとに分かれてグループディスカッションを行い、課題の深掘りや意見交換を行います。業種関わらず各社、情報のGive&Takeを前提に活動します。
報告動画はこちら»
-
AI研究会
自社事業の高度化/効率化に資するAIに関する研究
昨年度は、まさに生成AIが飛躍的な進歩を遂げ、注目された年となりました。皆様の周りでもChatGPTなどの話題が尽きず、それらのビジネスへの活用の可能性について意見を求められることが増えているのではないでしょうか?
技術の発展に伴って様々なツールが出現し、AIはまさに大きな転換点を迎えようとしています。当研究会は、活用推進/開発/ユーザーなど様々な立場でAIに関わる参加者が、各々のニーズ/スキルを踏まえ、技術、ビジネス活用、事例研究、理論、倫理、組織形成、教育などのテーマに分かれて研究を進めます。
報告動画はこちら»
-
デジタル変革リーダー自己育成
研究会
自らを「DXを通じた価値創出を主導するリーダー」に育成する手がかりを探る研究
~どうしたら我々は経営から現場にわたる「企業組織というプロダクト」の価値を高める人物になれるだろうか?~
自分自身を「DXを主導するリーダー」に育成していくすべを探究します。外部の知見に学ぶ機会を通じて視野を拡げ見識を深めると共に、目標となる存在や考え続けるべき問いとの出会いを期します。
また、ワーク・議論の場では参加者自身が「価値創出とは」「リーダーとなるには」を自分ゴトとして考え抜き、学びを咀嚼して行動につなげることを目指します。
報告動画はこちら»
-
トランスフォーメーション研究会
「トランスフォーメーションすべきものは何か」を見つけ出し、どのような変化が起きるのかを探る。
多くのDXプロジェクトが思ったような効果が得られない原因の一つに、DXのDの方にばかり意識が向いていることが挙げられます。大切なのはXの方であり、「何をどのようにトランスフォームしていくことが必要なのか」について考えることではないでしょうか。
様々なジャンルのトランスフォーメーションについて、ゲストスピーカーのお話をヒントにメンバーとのグループディスカッションを行うことでこれからの社会の変化の兆しに気づきを得ることを目指します。
報告動画はこちら»
-
人材育成事例(HRCS)研究会
人材に関する各社の実際の取り組み事例をもとにディスカッション
各社の人材育成、人材支援策の取組みをテーマに、参加者が期間中必ず1回以上の事例発表を行います。事例発表後、発表テーマを元にグループディスカッションを行い、課題の深掘りや意見交換を行います。発表テーマは採用、評価、育成、能力開発、働き方(テレワーク等)に関する内容を想定しています。
報告動画はこちら»
-
製造業DX推進アプローチ研究会
製造業DXを組織横断型で実現するための推進アプローチの研究
製造業におけるDX推進の課題・解決アプローチを研究します。
DX推進阻害要因としてPeople/Process/Technology観点などから切り口を見つけ出し、皆さんの関心度の高い研究テーマ(チーム)で深堀をして頂きます。
23年度は「DX提供価値の可視化・テーマ選定/DX推進に向けた経営資源の調達/スマートファクトリー×サイバーセキュリティ」がテーマとなりましたが、24年度は参加頂いた皆様からのアンケートなどを基に、研究テーマの絞り込みを行います。
報告動画はこちら»
-
デジタルマーケティング研究会
『IT/デジタル技術を駆使してビジネスインパクトを生むにはどうしたらよいか?』
本研究会は、このような経営層や事業部門の方からの質問にまっすぐ向き合う方で知恵を出し合い、学びあう研究会です。事業・マーケティングの視点を取り入れ、研究を進めます。
具体的には、以下の3つのアプローチを軸に研究会をすすめます。
1.マーケティングの専門家や、第一線で活躍中のマーケターの方による講演の開催
2.書籍・各社事例によるデジマ活動の咀嚼
3.特定テーマ(JUAS会員企業増, Z世代, BtoBマーケ, etc.)を題材にしたケーススタディや分科会活動、有志勉強会
報告動画はこちら»
-
ビジネスリレーションシップ研究会
プロジェクト企画から運用まで、多様なステークホルダーの役割分担と協調活動
「ユーザー部門」「情報システム部門」「経営」「ベンダー」「コンサルタント」など多様なステークホルダーがそれぞれの専門知識、経験を活かした協業【リレーションシップ】がプロジェクト成功のカギとなります。本研究会では、役割分担、握り方(合意形成)、契約(可視化)など、ステークホルダー間での良好な【リレーションシップ】実現のために必要な事象を研究します。
報告動画はこちら»
-
新規事業創出研究会
社会課題や身の回りの課題を解決する新規事業を創出するための行動特性、スキルセット、プロセスの研究をテーマに活動します。新規事業開発において必要となる「アントレプレナーシップ」を社会課題の解決に繋がる実テーマベースで考える/研究会の活動でもイノベーションを生み出すためのアイデア・手法を積極的に取り入れる/自社事業・自分自身の業務経験と離れたところから考えてみる、を研究会における活動方針とします。活動の柱は以下の通りです。
1)新規事業の実践経験のある講師によるゲスト講演の開催
2)国内外の新規事業事例をビジネスモデルの視点からその成功要因を分析する
報告動画はこちら»
-
女性ビジネスリーダー研究会
当研究会では、女性ビジネスリーダーの視点から経営戦略を探求し、参加者が個々の視点を高めると同時に、新たな視点を得ることを目的としています。
また、得られた知見は、参加企業に持ち帰り、実践に役立てることを目指しています。
さらに、この研究を通じて、個々の参加者がライフやキャリアの様々なイベントに直面した際に、助言や支援を求め合えるような、企業を越えた女性管理職のネットワークが構築されることも期待しています。
女性のみで検討することにより、女性特有の課題に焦点を当てた解決策の探求や、自信とアイデンティティの強化も期待されます。
報告動画はこちら»
-
関西 PARK2.0
(The Place of Advanced Relationship in Kansai)
関西地区のミドルマネジメントの方々が、ITに関する幅広い課題について本音の意見交換や議論をする場
研究テーマに関する討議(動向調査や事例紹介を含む)を行い、ミドルマネジメントの視点に立って研究成果(独自の有用な知見、指針、提言など)を創り出すと共に、活動を通じてメンバー間の情報交流を深めます。
報告動画はこちら»
アドバンスト研究会

公募によりグループを募集。
既存の枠にとらわれず、テーマ選定を含めて、自主運営タイプの研究会です。
-
情報共有研究会
情報システム部門では基幹系に比べて軽視されがちな情報系の仕組みに焦点を当て、社内のナレッジを有効に利用する方法(情報共有・活用)について研究する。
報告動画はこちら»

-
データエクスペリエンス研究会
- Data and beyond -
人間中心の立場からデータが持ち得る意味や効能を探求・整理し、データが果たし得る人間や社会への意義を研究することを目的に2018年度より研究活動を行ってきた。6年間の研究でビジネスの意思決定にデータがより良く活用できるようにする方法論とフレームワークを構築し、昨年度にはオープンセミナー「データ分析」と「価値創造」の断絶(ラストワンマイル)の越え方ワークショップ」 を実施しビジネス現場での有用性が確認できた。今年度は、より実効性の高いメソッドへの洗練に向けた実務での実証研究と、議論の多様性を確保するための研究会外との対話機会の創出を行う。
報告動画はこちら»

-
企業の成長戦略とDX投資研究会
2018年に経産省がDXレポートを発表したことを契機に、DXという言葉が浸透したが、実態として各企業におけるDXの取り組みはどこまで進んでいるのだろうか。デジタル技術の活用を目的化する事例も見受けられるが妥当なのだろうか。一方、企業が長期的な成長をしていくためには、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)すべての要素を考慮した経営が重要との見方が広まり、その実現にはDXが欠かせないと言われているが、企業の取り組み状況はいかなるものであろうか。本研究会では、ESG経営の先行企業におけるDXの取り組み状況を調査し、DXとESGの関係性について考察する。
報告動画はこちら»

-
システム高度化研究会
日本の国際競争力は’90年代後半から急激に低下した。様々な要因のうち、この時期に諸外国において進展してきた情報システムの活用が、日本では不十分だったことが考えられる。システム高度化プロジェクトでは、2017年より5年間に渡る検討を行い、ビジネスとITが一体化した「データ経営」と、それを実現するためのシステムのあり方を「データ経営が日本を変える!」という報告書にまとめた。その後もデータ経営を実現するためにDOBA(データ中心型ビジネスアプローチ)の実践について検討を継続し、更なる日本の情報システムの高度化の重要性についてアピールしていく。
報告動画はこちら»

-
哲学×ビジネス研究会
ビジネスに哲学を活用する動きが増えています。GoogleやAppleをはじめ、世界的企業が企業専属哲学者をフルタイムで雇い、CPO(Chief Philosophy Officer)、最高哲学責任者をおく企業もあります。
哲学は仕事やキャリアにおいて自己実現や倫理的な指針を提供し、論理的思考や協力関係の構築に役立つといわれています。哲学的な考え方、哲学をどのようにビジネス、働き方、組織に取り入れていけばよいのか、そのステップや方法について研究します。
報告動画はこちら»

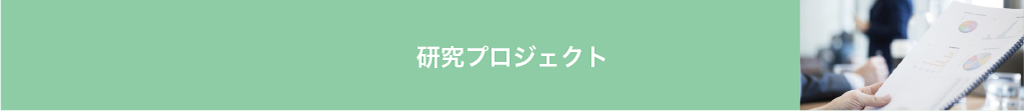
会員企業以外にも、学術関係者、専門家を加えたチームを編成し、広く意見・知見を求め、成果物を作成します。
-
未来ビジネスフォーラム
最新技術を使った新規ビジネスや既存のビジネスプロセスの改善などデジタル化に関わる各社の取組み状況に関して意見交換を行います。
-
基幹系システムアジャイル適用
研究プロジェクト
今までの活動で基幹系システムにアジャイルを適用するために乗り越えるべき壁を定義し、その解決策について示してきた。2024年度はさらに「アジャイル人財の育成と評価」「アジャイルの品質の捉え方」など6つのテーマについて検討します。
報告動画はこちら»

経営とITに関するさまざまなテーマについて、おなじ目線で情報共有し、意見交換を行います。JUAS会員活動の核となるユーザー系企業限定の活動です。主に東京と関西で開催しています。
-
CIOエグゼクティブフォーラム
ユーザー企業IT担当役員の方々のための経営とITに関する学びの場・交流の場
-
IT部門経営フォーラム
ユーザー企業IT部門長の方々のための経営とITに関する学びの場・交流の場
-
IT企業TOPフォーラム
ITグループ会社のトップの方々のための経営とITに関する学びの場・交流の場
-
ITグループ会社経営フォーラム
ITグループ会社の経営層の方々のための経営とITに関する学びの場・交流の場
-
人材育成フォーラム
ITグループ会社における人事責任者の方々のための、人材育成方針やこれからの企業・組織を担っていく人材を育成する実践策に関する学びの場・交流の場
![]()